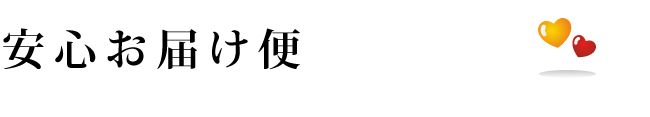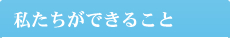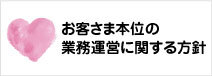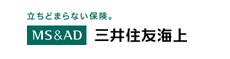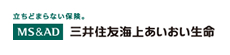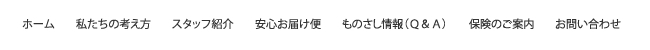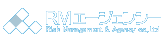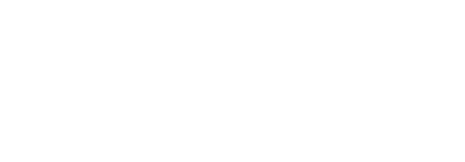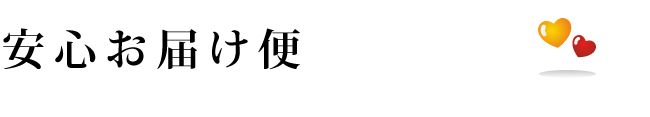
下記の内容を含む情報をお届けするとともに、日常業務における出来事を通して当社の基本姿勢や考え方をお伝えします。月に1回程度(不定期)、ご登録のEメールアドレスへご案内をお送りします。
よりいっそう、皆様のお役に立てればと考えております。
是非ご登録いただき、日々の「安心と安全」に生かしてくださればと思います。
2024年
04/05
4月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
バック事故防止のポイント
安全運転のポイント 2024.4月号
2024年
03/05
3月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
合流時における留意点について
安全運転のポイント 2024.3月号
2024年
02/06
2月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
特定小型原動機付自転車の特徴や事故防止のポイント
安全運転のポイント 2024.2月号
2024年
01/09
1月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
乗用車の日常点検について
安全運転のポイント 2024.1月号
2023年
12/07
12月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです
↓冬期、降雪、積雪時の安全走行について
安全運転のポイント 2023.12月号
2023年
11/07
11月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです
↓単路と交差点における「見えない危険」について
安全運転のポイント 2023.11月号
2023年
10/06
10月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです
↓薄暮時の死亡事故の特徴と事故防止のポイント
安全運転のポイント 2023.10月号
2023年
09/11
9月の安全運転のポイント
News | くらしと健康 | 交通安全 |
今月号はこちらです
↓異常事態への対応の仕方
安全運転のポイント 2023.9月号
2023年
08/10
8月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
運転時の注意の仕方についての留意点
安全運転のポイント 2023.8月号
2023年
07/06
7月の安全運転のポイント
News | 交通安全 |
今月号はこちらです↓
事故のない行楽ドライブをするための留意点
安全運転のポイント 2023.7月号