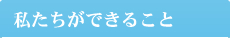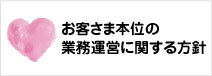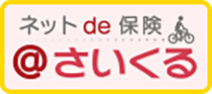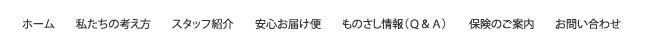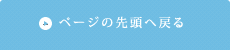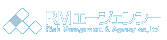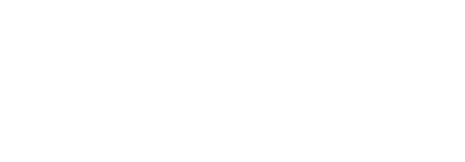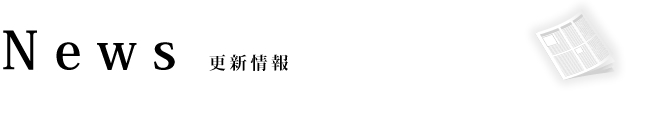
RMエージェンシーからのお知らせ、更新情報のページです。
- 2025/05/07
- 5月の安全運転のポイント
- 2025/04/04
- 4月の安全運転のポイント
- 2025/03/14
- 健康経営優良法人2025に認定
- 2025/03/06
- 3月の安全運転のポイント
- 2025/02/06
- 2月の安全運転のポイント
- 2025/01/07
- 1月の安全運転のポイント
- 2024/12/26
- 年末年始お休みのお知らせ
- 2024/12/05
- 12月の安全運転のポイント
- 2024/11/05
- 11月の安全運転のポイント
- 2024/10/18
- R6年12/4開催「運送業経営者様向けセミナー」のお知らせ
- 2024/10/04
- 10月の安全運転のポイント
- 2024/09/05
- 9月の安全運転のポイント
- 2024/07/22
- 8月の安全運転のポイント
- 2024/07/04
- 7月の安全運転のポイント
- 2024/06/25
- 健康経営優良法人2024に認定
- 2024/06/04
- 6月の安全運転のポイント
- 2024/05/02
- 5月の安全運転のポイント
- 2024/04/05
- 4月の安全運転のポイント
- 2024/03/05
- 3月の安全運転のポイント
- 2024/02/06
- 2月の安全運転のポイント